サイロス・シルボサ=ミラド(植物生存の解読:環境適応の機構の解明)
フィリピン大学 ミンダナオ校 生物学部 生物科学環境学科/
京都大学大学院 理学研究科 生物科学専攻 生物物理学教室 京都大学 化学研究所
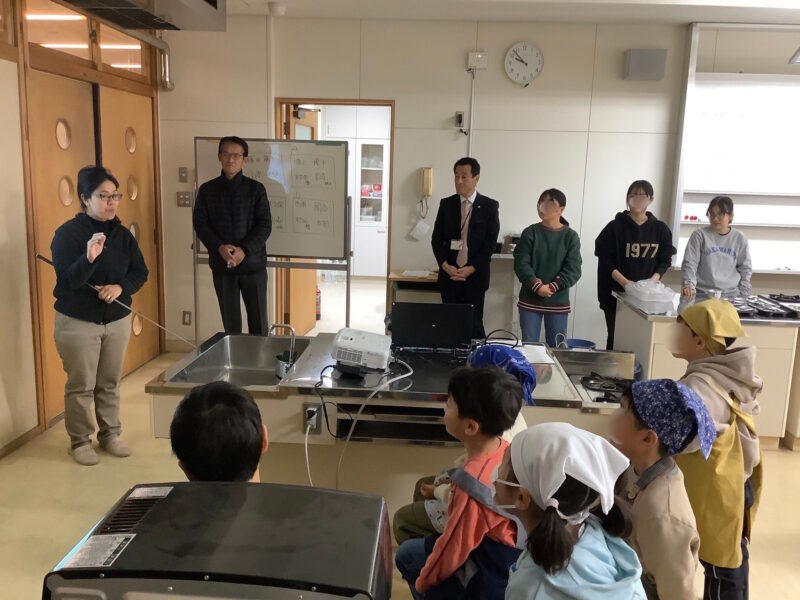
研究テーマ及び背景
筆者はフィリピン大学ミンダナオ校の助教、サイロス・シルボサ=ミラドであり、現在、京都大学大学院理学研究科に在籍し、化学研究所分子生物学研究室において柘植知彦准教授の指導のもと博士取得に取り組んでいる。筆者の研究は、植物のストレス適応、特に環境刺激に反応し遺伝子発現を制御する分子機構に焦点を当てている。博士課程に進む以前には、筆者は持続可能な農業、保全、分子遺伝学に焦点を置いた研究を行ってきた。これまでの研究内容は以下の通りである。a) フィリピン食虫植物ネペンテス・トランカータ(Nepenthes truncata Macf.)の植物体用有機培地に関する研究(理学士・生物学専攻、フィリピン大学ミンダナオ校)、b) 野生マメ科植物ハスノミツル(Lotus japonicus)の遺伝解析(植物遺伝学及び作物改良修士課程、イーストアングリア大学、英国)。フィリピン大学ミンダナオ校において、プロジェクトスタッフまたはプロジェクトリーダーとして研究領域をマイクロプロパゲーション、作物生産、植物形態学及び生理学に拡大した。2019年から2024年にかけて、フィリピンゲノムセンター・ミンダナオ・サテライト施設(PGCMin)において、分子同定技術を生物多様性及び作物研究に応用する業務に携わった。この経験により、分子バイオテクノロジーを持続可能な用途に活用する「バイオエコノミー」への関心を深め、これが現在の博士号研究の方向性に影響を与えている。
日本における博士研究
研究課題及び目的
植物は環境ストレスに対して、複雑な分子シグナル伝達経路を通じて絶えず反応している。筆者はシロイヌナズナ(Arabidopsis thaliana)のヌル変異体を用いて、ストレス条件に晒された植物が、分子レベルにおける発生・進化(development)の制御を解明することを目指している。これらの機構の理解は植物科学を超えた広範な意味合いを持つ可能性がある。なぜなら、多くの遺伝子制御ネットワークは、植物と哺乳類の間で進化的に保存されているからである。したがって、本研究では、環境ストレス下における植物の可塑性を制御する遺伝子発現調節に関する研究を以下の手法で遂行する予定である。

期待される成果
- 科学的貢献:環境ストレス下における植物の遺伝子発現及び転写制御に関する知見を拡充し、植物が外部刺激に適応するために可塑性を維持する仕組みを洞察する。
- 潜在的応用:得られた知見は、レジリエンスのための作物育種、植物及び哺乳類に共通するストレス反応経路に基づく生物医学研究、食品生産、バイオ医薬品、バイオマテリアルにおけるバイオエコノミー・イノベーションの推進に資する可能性がある。
- 長期的影響:将来の植物バイオテクノロジー研究の知識基盤を確立し、農業分野における気候変動への適応を支援し、日本とフィリピン間の植物分子生物学における研究協力を強化する。
本研究がフィリピン及びミンダナオにもたらす利益
本研究は、先端的な分子技術を研究及び教育に統合することにより、植物バイオテクノロジー分野における能力構築を強化する。得られた知識は学生、教員、教育機関に共有され、地域における専門性を高める。京都大学、MJ-STeP、フィリピン大学ミンダナオ校との連携により、農業及びバイオエコノミー分野における研究機会が拡大する。長期的には、本研究は気候変動に耐性を持つ作物の開発、食料安全保障の向上、持続可能な農業の推進に貢献する可能性がある。農業及び生物医学分野への応用を視野に入れたバイオテクノロジー及び分子科学における革新を促進し、グローバルな持続可能性の取り組みにも整合する。
